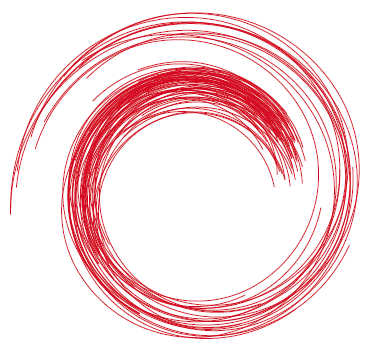第六回目は、当講座主担当の岸上有沙より「第三者評価とESG情報:その整理と活用」をテーマに講義し、後半は、日本総合研究所の足達英一郎氏を迎え、対談をしました。
第一回目の総論講義にて説明のあったサステナブル投資の生態系の中では、今回は評価機関に当たります。
講義では主に以下に関して、説明がありました。
- ESG要素を加味した情報がもたらし得る効果:個人的体験踏まえて
- 評価の担い手の変化と、そこで生じる課題OR醍醐味
についてです。
始めに岸上より、長期目線の経営者を支える金融システムを構築するという問題意識と、その仕組みの一つとしての指数を作成していたFTSE Russell社が組み入れ対象となる日本企業との対話を強化したいというニーズが合致し、関わり始めたという出発点が紹介されました。
同社は、2002年ごろから単に指数を作成するだけではなく、組み入れ企業における評価基準の理解を深め、そして投資判断ツールとしての指数のボラティリティを緩和するためにも企業の行動改善が確認出来る様、企業との対話チームを立ち上げました。
日本企業との対話強化のために岸上が2007年に加わり、2011年には奇しくも東日本大震災と同時期に原子力発電における安全性と透明性に関する基準が強化され、2017年にGPIFに初めてESG指数が採用されるまでの日本におけるサステナブル投資の変遷と、その中での個人的な関わりを紹介しました。GPIFによるESG指数の選定は、長期目線での投資家が増えることへの期待、役員が担当者の声に傾けやすくなったことなど、当時、企業からのポジティブな声に繋がったことが紹介されました。
この様に、「ESG/サステナブル」指数において、評価基準の説明を兼ねた企業との対話を指数会社自らが行うことが多かったですが、最近ではその指数を採用したアセット・オーナーの委託運用機関が、評価機関の情報を参考にしながら対話を行うなど、役割に変化が起きていることも紹介されました。ヨーロッパの事例として、指数に基づいた運用であっても内在されたリスクを軽減するための対話を行い、それでもリスクが減らない企業に対しては投資額を減らすことや投資対象から外すといった一定の運用の上での指数からの乖離も許容される運用手法が紹介されました。
ここ数年で、当初の目標であった、「ESG要素の情報が特殊なファンドだけではなく、通常の投融資判断に考慮される」システムが出来上がりつつある様に思われます。しかし、それ故に評価の枠組みや評価結果に関する様々な課題が浮き彫りとなり、日々情景が変わる過渡期にあり、ESG評価と情報がコモディティ化されてきていることが観察されます。この状況を「課題」や「乱立」と見るのか、それとも「評価に関わる醍醐味」や「多様性」と捉えるのか。その問いへの答えを受講生それぞれが導き出すためにも、実際に未来の基準作りを実践し、その内容や考察を共有頂きました。
日本総合研究所の足達氏との対談の前に、足達氏のこれまでのご経験を話していただきました。
1998年に金融ビッグバンを受けて銀行の窓口で投資信託の販売が始まり、その流れでエコファンドを親会社の住友銀行(当時)と共に考案・販売しました。日本では数社が同時期にエコファンドを立ち上げました。当時の記憶として、欧州を中心に各国の評価機関を訪問した際、低所得層コミュニティにオフィスを置いているところ、出版会社から派生したところなど、決して煌びやかではないけれども、志を持って、未来の金融システムへの期待を胸にどの評価機関も活動していたこと等を共有頂きました。
対談では、欧州と日本企業との2000~2010年当時の「ESGに目を向けた投資家」の受け止めの違いや、日本と欧州の機関投資家の評価機関へのリクエストの温度差や、GPIFによる指数選定を受けて日本企業や投資環境の変化や、欧州におけるインベストメント・チェーンの問題意識等が議論されました。
※執筆担当…岡田敦(JSIF運営委員)、岸上有沙(当講座主担当およびJSIF理事)