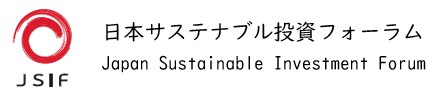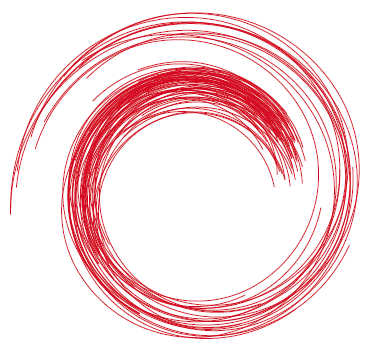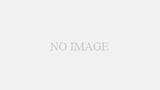PRIとGSIAのESGに関する投資方法の比較
PRIとGSIA の分類について整理比較したのが次の表である。

ESGインコーポレーションとサステナブル投資
この章の課題であるESGについて注目すると、次の違いがある。
- PRI分類では、原則1でESG incorporationとESG integrationの2つの用語が使われている。GSIA分類では、ESG integrationという言葉のみが使われている。これはPRIのESG integrationと同義である。
- GSIA分類ではESG incorporationという言葉は使われていない。GSIA分類では投資手法全体を示す言葉にサステナブル投資という言葉を使っており、PRIの原則2に該当するエンゲージメントと議決権行使もサステナブル投資に含まれる。
- PRI分類では、原則1に該当するESG incorporationを実現する投資方法を4つ取り上げており、そのうちの一つがESGintegration である。
- PRI分類では、原則1を満たす投資方法がESG incorporationである。そして、原則2のアクティブ・オーナーシップであるエンゲージメントと議決権行使は、ESGインコーポレーションには含まれない。つまりエンゲージメントと議決権行使のみを運用に適用する投資方法は、ESG incorporationとはされない。
インパクト投資
もう一つの違いが、インパクト投資・コミュニティ投資である。最近では、日本でもインパクト投資が盛んに議論されるようになっている。海外でも同様である。
- GRI のサステナブル投資には、インパクト投資・コミュニティ投資が含まれるが、PRI のESGインコーポレーションには含まれない。
- 詳細にPRI の報告フレームワークの用語集を読むと、パッシブ戦略では、インパクト投資とマイクロファイナンスをサステナビリティ・テーマ型としている、との解説がある。
- また、PRI のウェブサイト上にある資料などの説明からは、インパクト投資が含まれていない理由は、伝統的なインパクト投資がインパクトの成果を重視し、必ずしもリターンやリスクを考慮していないためだと理解できる。ただし、最近では年金基金などがそうした点を考慮したインパクト投資に取り組むようになっており、それを排除していない。
- この点を理解するには、PRIは年金基金などのアセット・オーナーが、ESGの課題を投資プロセスに組み込むことを広める目的を持つことを理解する必要がある。年金基金には、投資についてのフィデューシャリー・デューティー(受託者責任)やプルーデント・マン・ルール(思慮深い投資家の原則)があり、その範囲で投資を行う必要がある。詳細は省くが、過去には、ESG要因を投資判断に組み込むことは、投資のリターンを犠牲にすると考えられており、これが年金基金にESG incorporation が広まらないネックとなっていた。PRIの活動が広まり理解が進んだ現在では、逆に、ESGを考慮しないことがフィデューシャリー・デューティーに反するとまで言われるようになっている。いずれにしろ年金基金では、リターンを犠牲にすることは許されない。
- 時代が変化して、年金基金もインパクト投資を取り上げるようになったが、その際にはフィデューシャリー・デューティーを満たす範囲で投資するようになっている。PRI も、時代の変化に応じて、今後、分類や定義を多少改定する可能性もあるのではないかと個人的には考えている。
- GSIA の分類にはインパクト投資が以前から入っている。SIF は1920 年代に始まる社会的責任投資(その後サステナブル投資と呼ばれるようになった)の流れを受けており、1991年には英国のUK SIF が組織されていることから、年金以外の投資家も含めて歴史的に使われている主な投資方法をカバーしている。
全文は下記のPDFファイルをダウンロードしてお読みください。